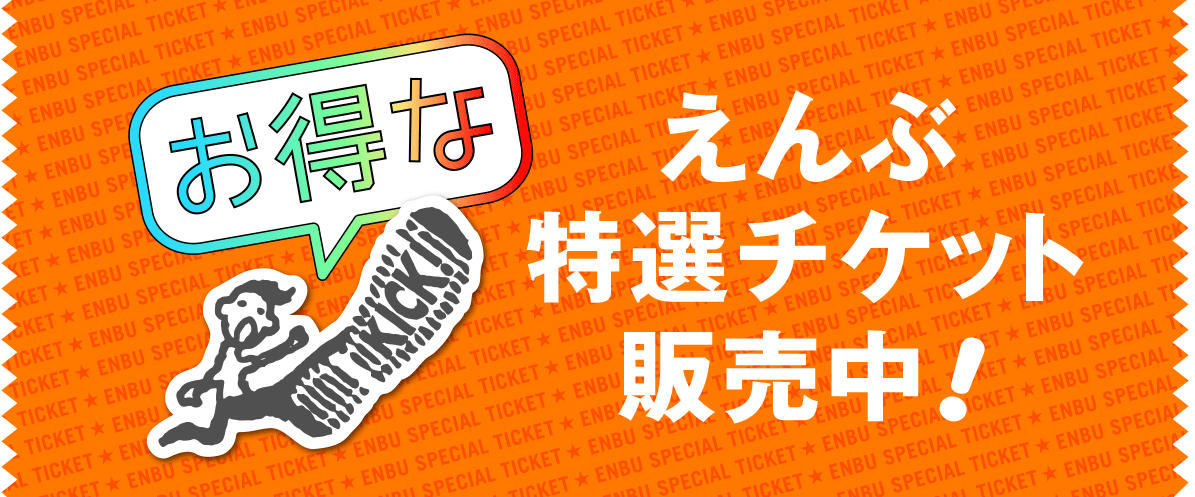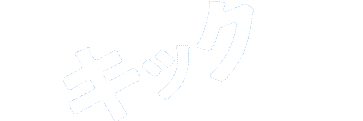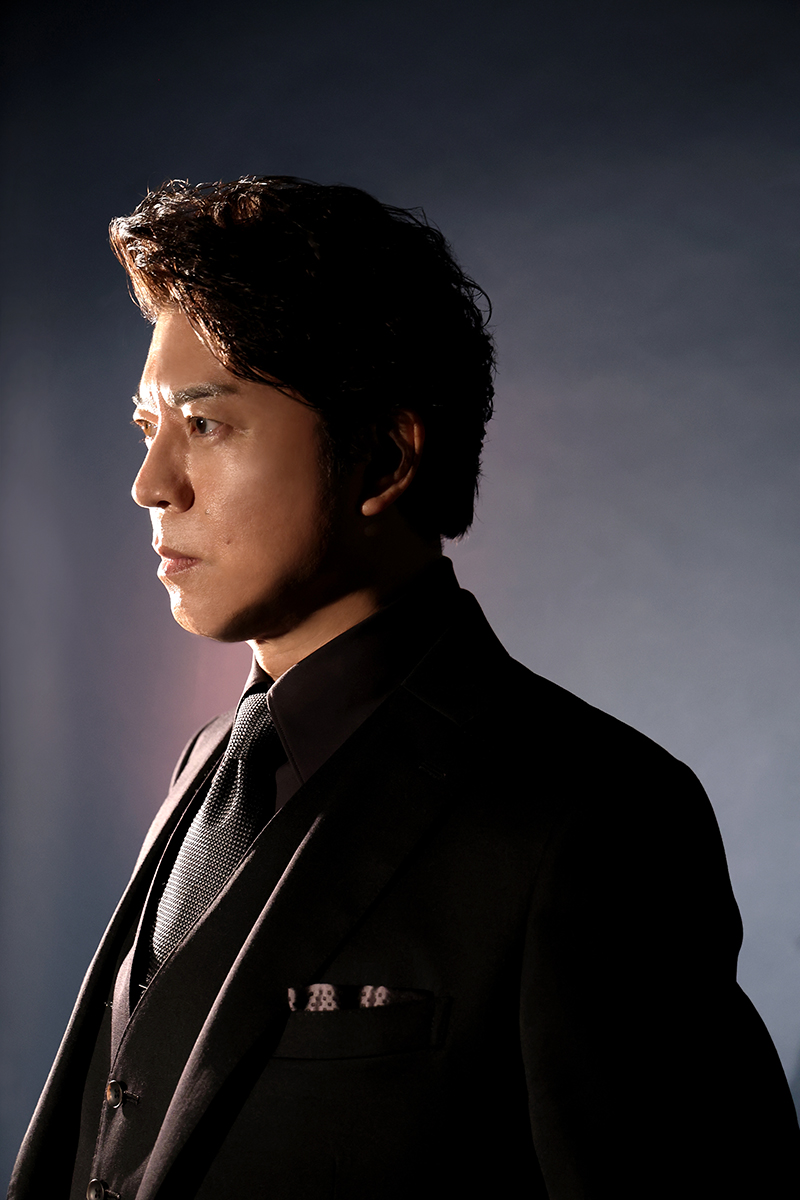
大石内蔵助役を遊び尽くし、楽しみ尽くしたい
名作『忠臣蔵』の世界が、討入りの月、12月に明治座で上演される。演出をエンターテイメント演劇の巨匠・堤幸彦が手掛け、松の廊下の刃傷はなぜ起きたのか、なぜ仇討ちは実現出来たのかなど討入りの真実に迫り、謎を解き明かす新たな歴史ドラマとして立ち上げる。物語の主役となる大石内蔵助は、今考え得る最高の大石役となる上川隆也が演じる。そんな大作『忠臣蔵』の世界と、「演じることの楽しさ」について上川隆也に語ってもらった。
武士社会の歪みやジレンマが、一気に表出した討入り
──まず『忠臣蔵』の大石内蔵助という役のお話がきたときの気持ちから聞かせてください。
正直申しまして、僕ごときのところに舞い込んでくるお話だとすら思っていませんでしたので、驚きと有り難みを素直に感じました。世の中にはこんなことも起こり得るのだな、という思いを抱いたというのが正直なところです。
──『忠臣蔵』という作品についてはどんな印象をお持ちでしたか?
今もお話しさせていただいたように、大石内蔵助を演じることなど夢にも思っておりませんでしたから、それにともなってある種の距離感はありました。もちろん時代劇の珠玉の1作品として映像や舞台で拝見はしていましたが、僕自身としては黒澤明監督の『用心棒』や『椿三十郎』などのような、スカッと明快で好漢が悪を討つというような作品を好んでいたものですから、『忠臣蔵』のような政治がらみの時代劇は、少し敷居が高いものとして感じていたのは確かです。
──今回演じるにあたって『忠臣蔵』の背景となる史実なども調べられたそうですね。
この役をいただいて改めてこの物語に向き合ったときにまず感じたことが、事件の発端となる勅使饗応役のことで、天皇の代理である勅使を迎えてもてなす、その饗応役を持ち回りでありながらも武士がつとめなければいけないという、その歪さなんです。もちろん武士が天下を取ったことで、政を執り行っていたのは武士ですから、その役目を担うのも当然なのですが、武士としての本来の役割との乖離が、この時代、元禄の世に生じていた。そのことを彼らはどう感じていたのだろうかと、そこに思いを馳せてしまうのです。もしかしたら「ありたい姿」と、今望まれている姿とのジレンマが、最終的に討入りという形に収斂していったのではないか、とすら思える。もちろんこの元禄繚乱の時代を甘んじて謳歌していた人たちもいたでしょう。ただ、そうではない、武士たらんとした人たちも一定数いたのではないかと。いてもおかしくないと思うんです。となると、本来は両成敗であるべき殿中での刃傷沙汰が、一方は罰せられ、片方はお咎めなしで済んでしまった。そのことにより、実はどこかで澱のように溜まっていた武士社会の歪みやジレンマが、一気に表出するきっかけになったのかも知れないと、僕の中で納得があったんです。あくまで僕なりのですが。
奇しくも2本、この年末に『忠臣蔵』が上演される意味
──討入りの元禄14年は江戸幕府の成立から約100年という時期ですが、徳川の世になっても2度の大坂の陣や島原の乱など大きな戦もあり、それもなんとか治まって人々が平和を享受しはじめた時代ですね。
ようやく治まった戦国がよかったとは言いませんが、武士の武士たる姿まで失われていくことへの思いはあったのではないかと思います。史実によりますと、吉良邸の周りの民家も赤穂浪士に肩入れして、灯りを消してくれたり、少なからず討入りに力添えをしてくれたそうです。それはどこかで武士としての待ち望まれていた姿、と言ったら言い過ぎかもしれませんが、これぞ武士という思いは深く静かに人々の中にあったのかもしれない。また、こじつけかもしれませんけれど、テレビや舞台で『忠臣蔵』があまり観られなくなってしまった今、この年末に、奇しくも2本、劇団☆新感線さんと僕らが『忠臣蔵』を上演することになるというのは、やはりどこかで深く静かに、誰かが望んでいたものがあったからこそではないかとも感じられて、そう思うとこれは演じる甲斐のある作品であると、今は感じています。
──この2025年の日本にも漂う不条理感が、こういうお芝居を求めているのかもしれません。
僕は、自分が役者としての立場にある限りは、時代を説いてはいけないと思っていますから、「この作品を今と照らし合わせること」には言葉を及ばさないようにしたいのですが、彼らのあのときの強い思いには、どこか寄り添えるものが確かにあるのではないかと思っています。
──そういう意味でいえば、上川さんは時代背景が戦国から江戸初期という『真田十勇士』や『魔界転生』という作品を演じてきたことで、武士という役割の変化なども物語の中で体感しているとも言えます。
確かにそうかもしれませんし、どこかで肌感覚としてわかる部分はあるのかもしれません。芝居の中とはいえ、いっときでもそういう立場に身を置いたことがあるからこその共感は否めない気がします。ただ今回は、『真田十勇士』の幸村や『魔界転生』の柳生十兵衛のような、ある意味わかりやすい〈武士としての情熱の費やし方〉とは趣を違える部分がありますから、表現の方向性も巧妙な差し手が繰り広げられる将棋のような、ある意味大人の清濁併呑や狡猾さが必要になってくるのではないかと思っています。
「楽しむこと」で僕自身と役柄とがその物語の中で息づく
──この公演の製作発表で、上川さんが「作品の重みは受け止めたうえで、まずは舞台を楽しみたい」とおっしゃっていました。上川さんにとって「楽しむ」という意味を改めて教えてください。
僕にとっては〈演じること〉そのものが「楽しいこと」の1つなんです。それがあるからここまで続けてこられましたし、何よりも最大の原動力であることは間違いありません。これは作品によらず、いつでも自分の中では尽きないものとしてありますから、たとえ300年語り継がれてきた『忠臣蔵』というビッグネーム作品であろうとスタンスは変えずに臨みたいと思っています。僕はこれまで、自分から作品や役柄の訴求をしたことがなく、いつでも投げかけていただく作品や役柄を、新しいおもちゃをいただくように楽しんできました。だからこそ、これまでとは少し趣の違う、政治が大きく絡むような『忠臣蔵』という物語であったとしても、楽しめないわけはないでしょうし、この『忠臣蔵』という作品も大石という役柄も、きっと中に飛び込んでみたら、面白い世界がきっとある。それらが確信としてあるうえで、どこまで遊び尽くせるか、役者として楽しみ尽くせるかを、今回も限られた時間の中で見いだしていきたいと思っています。
──遊び尽くすための方法ですが、それは例えば大石内蔵助という人物になりきってそこで生きるという感覚なのでしょうか?
どうなのでしょう? 「そうです」と言い切る自信は正直ありません。と申しますのも、演じているのは僕自身にほかならないのですが、演じている自分を常に客観視している僕がいるんです。例えば右を選ぶか左を選ぶかわからないとき、右を選ぶのも僕ですし、「あ、右を選ぶんだ」と驚いているのも僕なんです。そんな、お芝居をしている最中に生じる主体と客体があって、でも同時に自分は自分であるという自覚は揺るがずにありますから、その役柄になりきっているかどうかも定かではない、変な感覚があるんです。ただ、その時間・その役柄・その物語を楽しんでいることは間違いない。楽しんでいればいるほど、その客観的視線もより明確になっていきますし、そのとき僕に見られている僕自身の選択肢も右、左にとどまらず、上、下、前、後ろと多岐に及んでいきます。そんなふうな感覚を、今この場で〈物語を味わい尽くす〉という言葉の中に込めました。味わっていけばいくほど、僕自身と役柄とがその物語の中で息づくというような感覚でもあり、そこに繋げていくための言葉として、何よりも「楽しむ」という言葉以外に説明のしようがない。ですからそういう意味合いとして使っているとしか申し上げようがないんです。
──「楽しむ」という域はとても奥深いのですね。そして公演をしている期間中は上川さんはずっとその役柄との遊びを楽しんでいる。
誤解を恐れずに言うなら、役柄とじゃれ合っているみたいな感じと申しましょうか(笑)でおります。
堤監督に何らかの企みやもくろみがないわけはない
──お話は少し変わりますが、最近主演されたドラマの「能面検事」や「問題物件」では、ちょっと特異な主人公を演じていました。新しい役柄にチャレンジしてみたいという願望もあったのでしょうか?
ないと言ったら嘘になってしまいますが、こればかりは物語や役柄に巡り会わないことには始まらないので。そう考えると自分はなんと運が良いのだろうという思いが、まずあります。
──その巡り会った特異な役をいとも簡単に自分のものにされているのにも驚くのですが。
簡単ではないです(笑)。ただ、どんな生き様にしていこう、というような思索はします。それが原作のあるものなら原作をあたりますし、そこから抽出できるものはできる限り掬い上げたいと思っています。また、付与できるものがあれば衒いなく試みますが、最後は監督の「あり、なし」の裁定に委ねたいと常々思っています。
──役を膨らませるアイデアなどは常に考えているのですか?
それに関しては、なんとなく頭をもたげていたアイデアがあって、どこか使えるところがないかと探ったりすることがある一方で、テストの瞬間に思いついてやってみたら監督が面白がってくださるということもあります。
──上川さんのそういうアイデアの源はどこにあるのでしょう?
やはりこれまで自分が読んできた小説や漫画、観てきた映画・ドラマまたはアニメーションなど、そういう様々なものの中で、面白いと思ったものが僕の中で醸成されて陽の目を待っているんでしょう。だからこそ不意に思いついてというようなことにもなっていく。いまだにアニメーションや漫画は好きなのですが、好きでいて良かったと思う瞬間でもあります。
──堤幸彦監督も様々な表現手法を取り入れて作る方ですが、今回はギミックは使わずストレートに作るとおっしゃっていました。
監督が物語という意味では本来のストレートな形で作られるとおっしゃっている一方で、何も企てていないはずはないと思っているんです(笑)。『魔界転生』のときも初演と再演では趣向を変えてきた方ですから、お客さまに対してのエンターテイメント作家の姿勢として、きっと何らかの企みやもくろみがないわけはないと。もちろん、お客さまを楽しませたいという堤さんの観客への思いはストレートなのではないかと思っています。
──堤監督らしい何かを考えていらっしゃると。
そう思います。それは高橋克典さんが吉良上野介役という配役にも感じています、この物語に新風を吹かせたいという思惑を。ここからも、堤さんのある種の企みの一端が、仄かながら見て取れるのではないかと僕は思っている、というか邪推しております(笑)。
──堤幸彦・上川隆也コンビのエンターテイメント時代劇が、また新しいフェーズを見せる一作になりそうですね。最後にお客さまへのメッセージをぜひ。
令和と元禄という2つの時代、そこには300年以上の隔たりがありますが、そこに息づく人々の喜怒哀楽に変わりはないと思います。それを忘れず、そして大事にしつつ、堤さんのもくろむ物語に大胆に臨みたいと思っております。そのもくろみがなんであったのかは、是非劇場で目の当たりにしていただきたいと思います。
(このインタビューは「えんぶ12月号」より転載)
プロフィール
かみかわたかや○東京都出身。1989年から2009年まで演劇集団キャラメルボックスで活動。在団中の95年、NHKドラマ「大地の子」で主役に抜擢される。以降、舞台、映画、ドラマのほか、バラエティや声優としても活躍中。主なドラマ主演作は、NHK大河ドラマ「功名が辻」、「遺留捜査」シリーズなど。近年の出演舞台は、日本テレビ開局65年記念公演『魔界転生』、NODA・MAP『Q』、『隠し砦の三悪人』、プレミア音楽朗読劇 VOICARION XVIII『Mr.Prisoner』、読売新聞創刊150周年記念・よみうり大手町ホール開場10周年記念舞台『罠』など。
インタビュー◇宮田華子 撮影◇中村嘉昭
公演情報

脚本◇鈴木哲也 演出◇堤幸彦
出演◇上川隆也 藤原紀香 立石俊樹 藤岡真威人 崎山つばさ
岐洲匠 石川凌雅 近藤頌利 藤林泰也 唐木俊輔 財木琢磨
松田賢二 徳重聡 珠城りょう 高橋克典 ほか
12/12~28◎明治座、2026/1/3~6◎御園座、2026/1/10◎高知県立県民文化ホール、2026/1/17◎富山県民会館、2026/1/24~27◎梅田芸術劇場メインホール、2026/1/31◎長岡市立劇場
〈公式サイト〉https://chushingura-ntv.jp