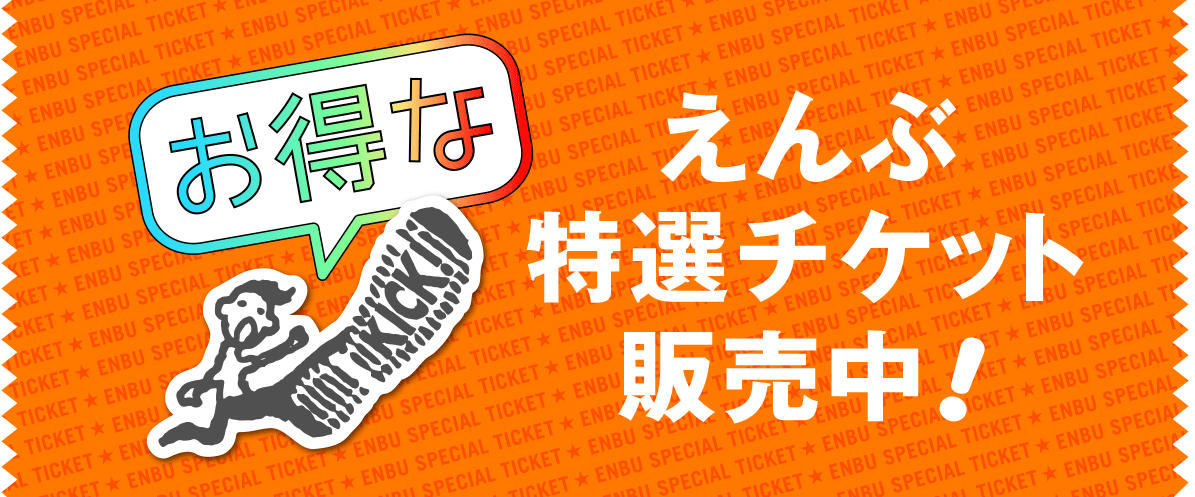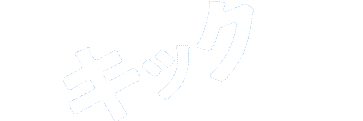ワタナベエンターテインメントと劇作家・末満健一がタッグを組み、日本のクリエイターたちの才能を集め、世界レベルの作品を創造・発信していくMOJOプロジェクト -Musicals of Japan Origin project-の第一弾、ミュージカル『イザボー』が、東京建物Brillia HALL(豊島区立芸術文化劇場)で上演中だ(30日まで。のち大阪オリックス劇場で2月8日~11日まで上演)。
ミュージカル『イザボー』は、フランス王とイングランド王との間の争いに領主たちの領土争いが重なり、フランス領内で繰り広げられた百年戦争の時代に、陰謀渦巻くフランス王朝で欲望のままに生き、フランスをイングランドに売り渡した最悪の王妃と呼ばれるイザボー・ド・バヴィエールの半生をドラマチックに描いた作品。 “生き抜くことへの肯定”を根底にした、ダークでありつつ独特のカタルシスを持つ『TRUMPシリーズ』で熱狂的なファンを持つ末満健一の脚本・演出。その末満と十年以上作品を作り続けている和田俊輔が綴るロックを基調にした圧倒的な音楽。3層構造で回転を続ける松井るみの独創的な装置。ドラマチックさを高める関口裕二の照明などのスタッフワークの結集と、タイトルロールのイザボーを演じる望海風斗を筆頭に、現在のミュージカルシーンに欠かせない個性的かつ、歌唱力豊かなキャスト陣が揃い、強い力感を持った新作ミュージカルが誕生している。
【STORY】
百年戦争の時代。
フランス・ヴァロア朝の第5代国王となるシャルル7世(甲斐翔真)は、戴冠式を目前に自らが戴く王冠と責務の重さに、高揚と共にある不安を感じていた。そんなシャルル7世に義母ヨランド・ダラゴン(那須凜)は、彼の実の母であるイザボーの生き様を知らなければならないと促す。それはフランスの歴史上で最も嫌われた、最悪の王妃の生きた道を辿っていくことだった──。
バイエルン公の娘として生まれた少女イザベル(大森未来衣)は、隣国フランスに嫁ぎ王妃、イザボー・ド・バヴィエール(望海風斗)となる。夫のシャルル6世(上原理生)はイザボーをこよなく愛したが、ある出来事を境に狂気に陥ってしまう。
破綻した王政につけいり、シャルル6世の伯父ブルゴーニュ公フィリップ(石井一孝)とその息子ジャン(中河内雅貴)は権力を掌握しようと画策し、女であるイサボーは政務に関わることを許されない。憤るイザボーにシャルル6世の弟オルレアン公ルイ(上川一哉)が加担し、対立するフィリップとジャン親子を攪乱。ほどなくイザボーとルイは不貞の関係となり、権力争いはさらに激化していく。そんな混沌の時代の中でイザボーは、自らの愛と衝動のままに生き抜こうとするが……

「ミュージカルファンはフランス革命に詳しい」というのは、最早定説と言ってもいい話だ。それほどフランス大革命前後を描いたミュージカル作品は数多く、フランス国王ルイ16世と王妃マリーアントワネットからナポレオンに至る間の話なら、滔々と語れるミュージカル通は枚挙に暇がないだろう。だが、それより300年以上前、フランスとイングランドの間に続いた「百年戦争」とのちに呼ばれることになった時代となると話しは違ってくる。もちろんこの時代に精通している方々もたくさんおられるはずだが、あくまでもミュージカルファンの間に周知されている時代か?というと、フランス大革命時代に比べればかなり認知度は低くなるだろうし、おそらく神の啓示を受け数奇な運命をたどったジャンヌ・ダルクの物語が最も知られている時代と言って過言ではないと思う。
だが、そんなジャンヌ・ダルクの人生については「また別の物語だ」と言い切ったこの作品が描いたのは、その百年戦争時代にフランスをイングランドに売り渡した、フランス史上最悪の王妃と呼ばれるイザボー・ド・バヴィエールを主人公にしたドラマだった。この斬新な視点が、日本発信で世界を目指すオリジナルミュージカルを!という旗を掲げて立ち上がったMOJOプロジェクトの第一弾に、大きなインパクトを与えることになった。
日本人が初めて日本語でブロードウェイミュージカルを上演した1963年から60年あまり、いまも欧米作品を輸入して、日本人キャストによる「日本初演」という形で上演する形態が、日本のミュージカル界の主流であることは変わっていない。ただ一方で、日本発信の、しかも世界に輸出できる作品を生み出していこうという試みもまた、そこここで動きを見せはじめている。そのなかでも大きな可能性を秘めているのは、日本が誇る一大コンテンツであるアニメーション作品の舞台化で、ミュージカルとは規定していないものも含めると、2.5次元と呼ばれる作品群を筆頭に、既に海外での上演が叶っている作品も多くあるし、非常に大がかりなプロジェクトがいくつも進行中だ。輸入に頼るのではなく、日本から世界へというムーブメントは演劇界、そしてミュージカル界のなかで確実に起こりはじめている。
そんな2024年、このMOJOプロジェクトが世界史に題材を求め、しかもスポットを当てたのが、演劇として、またミュージカルとしては語りつくされていない時代と人物だったことは、非常に優れた選択眼だったと思う。どんな内容なのかが全く未知数になる、作家の頭のなかにしかイメージがないフィクションの創作ものでもなく、実在の人物を扱っていながら適度に新味があり解釈の幅が広い。この絶妙なチョイスが、MOJOプロジェクトが踏み出した一歩に大きな期待を抱かせた。ここに鉱脈があると感じさせたのは貴重だし、何よりオリジナルの新作の良さで、いまの時代にはむしろ珍しいシングルキャストで出演するキャストがいずれも役柄によくあっている、ある種のあてがきがなされている効果には大きなものがあった。

その筆頭、タイトルロールのイザボー・ド・バヴィエールに扮した望海風斗の、ダイナミックな歌唱と、フルパワーを感じさせる演技が、如何にしてイザボーが「最悪の王妃」と呼ばれるに至ったか?を的確に表している。フランス語も話せないままバイエルンから嫁いできてフランス王妃となった少女が、愛した王が狂気に陥ったことで否応なく強さを身に着け、やがて本能の命じるままに権謀術数のただなかで生き抜こうとする。この1幕から2幕の間で、激変するイザボーの人となりを「Queen of the Beasts」1曲のなかでねじ伏せて見せたのは、アル・カポネ、ドン・ジュアン、恐怖政治時代に至るマクシミリアン・ロベスピエール、『ONCE UPON A TIME IN AMERICA』 のヌードルスなど、宝塚のトップスターとしては非常に珍しく、悪の香りを放つ役柄に多く当たった望海の個性と経験値の賜物。狂気に陥った夫を慮る憂いの表情が、いつしか悪の華とも言いたい不敵な笑みに変わっていく様にゾクリとさせる凄みがあり、どこまでもパワフルな歌声と共に、望海あったればこそ作品が成立したと思わせる当たり役ぶりを示していた。

主人公イザボーとシャルル6世の息子シャルル7世を演じる甲斐翔真は、母子としての実感が極めて薄く、悪評だけを聞き続けてきたイザボーの真実を学んでいく、という観客の視点に最も近い役柄を、恐れをにじませながら表現しているのがこの説明役をよく生かしている。特に大柄な体躯からくる安定感と、ふとした時に見せる子供のようにあどけない表情という、現在の甲斐自身が持っているアンビバレンツな魅力が、自信と不安が交互に押し寄せる作品のなかのシャルル7世にピタリとあった効果が絶大。舞台で起きている出来事を俯瞰しながら、意外な形で様々にドラマのなかにも加わっていくシャルル7世の描き方には、末満作品らしい遊び心もあり観る側にとっては或いは好き嫌いが分かれるところかもしれないが、そうした場面場面で求められる色に応えつつ、終盤に向けてイザボーを理解していく甲斐の真摯な芝居に、素直に胸打たれた。

イザボーの夫、国王シャルル6世の上原理生は、この人の舞台に常にあった自信に満ち溢れている感覚を一掃し、自らが制御できない狂気に落ちていく恐慌と孤独を全身で表出している。シャルル6世は己の身体がガラスでできていると思い込む「ガラス妄想」と呼ばれた精神疾患を患ったとされていて、それがどれほどの恐怖かを想像するだけでゾッとするほどだから、触れられることに怯える様が痛々しく真に迫る、上原個人にとっても新境地を感じさせる演技になった。

シャルル6世の伯父ブルゴーニュ公フィリップの息子ジャンの中河内雅貴は、父親と常に行動を共にしている冒頭から、ソリッドな感覚を漂わせているのがのちの展開に生きている。本来の持ち味には非常に熱いものがある俳優だが、ジャン役ではその熱さをひたひたと内に秘める情念に変換させていて、作品のなかで流れる時間で刻々と立ち位置を変えていくジャンの根底には強い愛国心があり、すべてはその信念から発せられる行動だと見えるのが興趣を深めた。

シャルル6世の弟オレルアン公ルイの上川一哉は、近年非常に多く語られるようになった王の弟、所謂「スペア」であることに対する捻じれから、うまく立ち回ったつもりの自分の意外な感情に戸惑う様を、ふり幅広く演じて魅了する。ダンス力と歌唱力の評価が高い人だが、近年の舞台では何よりの強みはこの深い演技力ではないか?と思わせる複雑な役柄を次々と見事に演じていて、今回のルイ役でもその感触を一層強め、複雑な心理描写に観応えがあった。

シャルル7世の義母ヨランド・ダラゴンの那須凜は、ミュージカル界の錚々たる面々が集まった座組のなかで、ミュージカル初挑戦という経歴が逆に信じ難いほど、生き生きと舞台に位置し、堂々と歌う様に驚かされた。シャルル7世と共に作品全体の語り部であり、そのシャルル7世をもリードしていく役柄を自在に演じていて、ミュージカル界にとって大変な逸材の登場を感じさせた。今後も是非ミュージカル作品への出演を続けて欲しい人だ。

シャルル6世の伯父ブルゴーニュ公フィリップの石井一孝は、言うまでもなく日本ミュージカル界を支えてきた一人で、座組にいるだけで安心感が増す存在。この人もまたラテン系を思わせるほど熱く陽性な個性の持ち主だが、その熱さを病の王を傀儡にして政治の実権を握ろうとする役柄にうまく生かし、より一層食えない人物に見せることに成功しているのがさすがにベテランの妙。にこやかに笑いながら、イザボーに立ちはだかる大きな壁として屹立していた。
そんなプリンシパルの面々がいずれ劣らぬ歌唱力を持ち、時に暴力的なほどロックなナンバーの数々を客席に届ける圧の強さは、観ている側にも体力がいると思わせるほど。それでいてフランスの命運が歌われる美しいメロディーのリフレインが印象的に耳に残るなど、多彩な工夫も盛りだくさん。工夫と言えば、イザボーの若き日を演じる大森未来衣がもうひと役で出てくる効果には、そう来たか!と膝を打つものがあり、大森の大器を感じさせる演技と共に非常に印象的。ルイの妻ヴァレンチーナを実直に演じる伯鞘麗名をはじめ、石井咲、加賀谷真聡、川崎愛香里、齋藤千夏、佐々木誠、高木裕和、堂雪絵、中嶋紗希、宮河愛一郎、安井聡、ユーリック武蔵の面々も、芝居にダンスにと大活躍。どんな状況に置かれたとしても、人生を諦めずに生き抜く人々が描かれる、視点を変えれば誰も悪人ではなく、ただ懸命に生きた人々の物語であるミュージカル『イザボー』に一人ひとりが厚みを加えていた。
また、シングルキャストを貫いた作品になくてはならない存在の、スゥイングとして舞台を支える井上望、齋藤信吾、高倉理子をカーテンコールで紹介したのも素晴らしい配慮だし、複雑に回り続ける舞台装置に無数に開いた開口部分からキャストたちが次々に顔を出す、観ている側としては大変面白いが、演じる側の負荷は相当なものなのではと想像できる舞台機構を人力で回すスタッフや、生演奏のメンバー、照明、音響など全てのスタッフワークにも直接拍手を贈る時間が設けられているのが嬉しい。ひとつの舞台はライトを浴びるキャストたちだけでなく、多くのスタッフが動いてこそ成立することを可視化したのは、MOJOプロジェクトがオリジナルミュージカルの大海原に漕ぎ出す上での矜持なのだ、と感じられるのが美しかった。
何よりこの遠い昔の、更に遠い異国の物語から、歴史がのちにどんな評価をしようとも、与えられた命を人は懸命に生き抜くべきだ、との真理が届けられたこと。あまりにも困難多き2024年の日本にそのメッセージが響いたことを、尊く受け止めたい舞台だった。

【公演情報】
MOJOプロジェクト -Musicals of Japan Origin project-
ミュージカル『イザボー』
作・演出:末満健一
音楽:和田俊輔
出演:望海風斗/甲斐翔真/上原理生 中河内雅貴 上川一哉/那須凜/石井一孝
大森未来衣 伯鞘麗名 石井咲 加賀谷真聡 川崎愛香里 齋藤千夏 佐々木誠
高木裕和 堂雪絵 中嶋紗希 宮河愛一郎 安井聡 ユーリック武蔵
スゥイング:井上望 齋藤信吾 高倉理子
●1/15〜30◎東京建物Brillia HALL(豊島区立芸術文化劇場)
〈料金〉S席12,500円/A席9,000円(全席指定・税込)※S席は1、2階、A席は3階
〈お問い合わせ〉サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12時~15時)
●2/8~11◎大阪・オリックス劇場
〈料金〉S席12,500円/A席9,000円(全席指定・税込)
〈お問い合わせ〉キョードーインフォメーション 0570-200-888(月~土11時~18時)
〈公式サイト〉https://isabeau.westage.jp/
【取材・文・撮影/橘涼香】