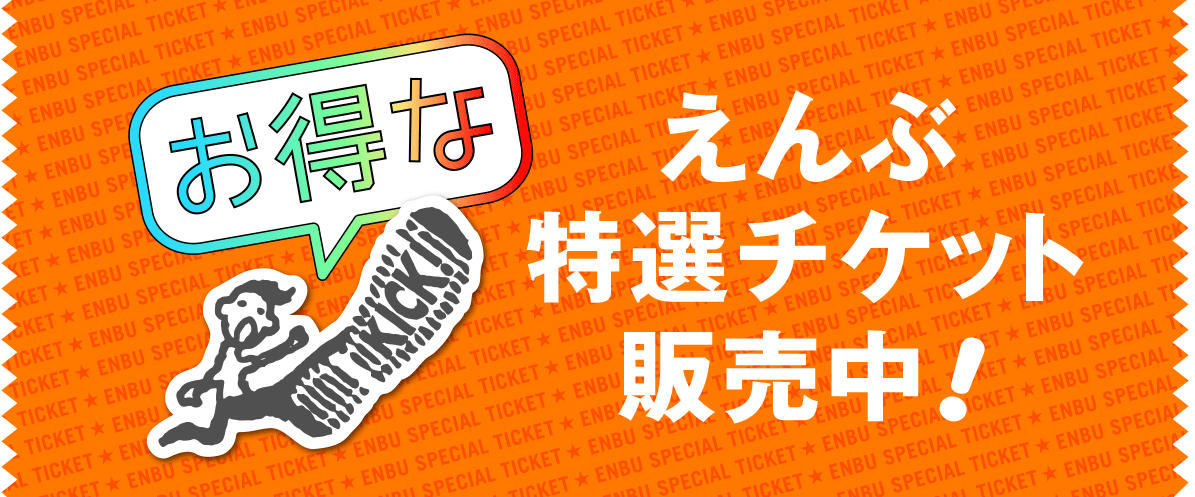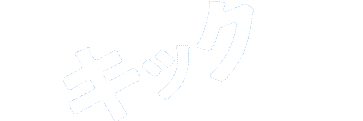この九月に松本から始まる劇団☆新感線「爆烈忠臣蔵」。稽古も大詰めです。豪華なゲストと旧劇団員たちも含めて勢揃いでお届けするオポンチ時代劇。今年いっぱいまでの公演ですから先は長い。気をつけて行きたいと思います。
「爆烈忠臣蔵」はタイトルの通り、締め付けの厳しい天保年間に「仮名手本忠臣蔵」を上演しようとする歌舞伎役者たちの物語です。ですので劇中劇として忠臣蔵の名シーンがいくつか出てきます。戦前には忠義の物語として、戦後には痛快娯楽劇として、舞台はもちろん映画やドラマとして何度も製作され、そのストーリーは一般大衆にも広く浸透していました。
ですが、今ではすっかり古びてしまい、最近ではその粗筋も知らない方も多いんじゃないでしょうか。私だって松の廊下の「殿中でござる!」とか、吉良邸討ち入りのシーンとかくらいしか知りませんでした。
でも、テレビプロデューサー・演出家・劇作家である小松純也さんの名作であり、こちらも忠臣蔵と歌舞伎役者を絡めたストーリーである「冬の絵空」という舞台に二度出演しているので、その時に勉強したことによってある程度は知ることができました。ただ、こちらも史実の赤穂事件と戯曲の仮名手本忠臣蔵、そして小松さんのフィクションが入り交じっていますので、ちゃんとした「仮名手本忠臣蔵」は知らなかったのです。
ですので、戯曲をちゃんと知っておこうと思いまして、現代語に訳された河出文庫の松井今朝子・訳「仮名手本忠臣蔵」(ちなみにこれは竹本座の人形浄瑠璃版)を読んでみました。そしたらねえ、やはり知らないことが多すぎて驚いたというワケです。
忠臣蔵について書く前に、まずは元になった「赤穂事件」についてご説明しておきましょう。時は江戸中期の元禄十四年三月十四日。朝廷勅使を饗応する役目を負っていた赤穂藩の浅野内匠頭長矩が、その指導役である高家筆頭の吉良上野介義央に対して江戸城松之大廊下にて斬りつけ、即日切腹となりました。その原因について浅野は弁明していませんが、どうやら吉良からパワハラを受けていたらしく、その恨みが昂じて刃傷に及んだようです。当時の江戸城内(殿中)での抜刀・刃傷は死罪断絶と決まっており、浅野の切腹と赤穂藩断絶は当然のことながら、吉良に対して何のお咎めもなかったことが赤穂藩士に遺恨を残したわけです。
そして翌元禄十五年十二月十四日。本所松坂町の吉良邸に赤穂家家老・大石内蔵助良雄を始めとする赤穂家浪人四十七名が討ち入って吉良の首級を挙げ、泉岳寺にある浅野の墓前に首を供えました。そして、赤穂浪士たちはいくつかの大名家に預けられた後に切腹することとなります。
以上がいわゆる赤穂事件の概要です。平和な江戸中期に武士の意地と矜持を見せたとして人々は喜んだそうです。そして歌舞伎や人形浄瑠璃などでこの赤穂事件をモデルとした作品が多く作られました。
そして、その中でも一番評判となり、現代まで上演され続けているのが「仮名手本忠臣蔵」というわけです。
討ち入った赤穂浪士が四十七名だったことを「いろは四十七文字」になぞらえたこの「仮名手本忠臣蔵」は、まずは人形浄瑠璃として大坂の竹本座で上演されました。この当時、江戸幕府に絡んだ事件をそのまま題材とすることは禁止されていたので、時代を南北朝時代に移し、浅野内匠頭を「塩冶判官高定」、吉良上野介を「高師直」という実在の武将に置き換え、大石内蔵助は「大星由良之助」としてあります。
実際の赤穂事件から約50年後に書かれたこの作品では、時代を変えてある事も含めてかなり史実とは異なるエンタテインメントとして作られています。もちろん全くのフィクションというわけではなくて、その時代の様々な風俗を取り入れて見所を配しているのです。
まあね、元々が侍たちの話ですので、どうしても侍の男たちが中心になってしまいますが、戯曲の忠臣蔵では勘平の女房・おかるや大星力弥の許嫁・小浪、判官の奥方・かほよ御前などの女性もたくさん登場して重要な役回りを演じます。それによって艶っぽいシーンや舞踊だけのシーンができたりすることでバラエティも豊かになります。
あと、それに関係してだかどうだか判りませんが、意外とセクハラまがいの下ネタや色っぽい場面が多いのも驚きでした。それも時代性なのかもしれません。
全体的に韻を踏んだ言い回しや言葉遊び、風情のある比喩など、リズムよく聞きやすい表現が巧みに配置され、娯楽作品としての完成度を高めているようにも思います。
この人形浄瑠璃が大評判となり、その年の内に歌舞伎としても上演されました。客入りの悪い時期でも忠臣蔵を上演すると大入になったのだそうです。そして明治以降は映画として、昭和以降はテレビドラマとして、人々に愛される作品となりました。毎年のように年末になると特番ドラマが放映されたり、バラエティ番組のコントとして広くお茶の間で楽しまれていました。ザ・ドリフターズが「殿中だ!」と叫びあいながら、お互いの長袴を踏んで転び回っていたりしてね。子供でも殿中の意味が判ったりしていました。
ですが、最近ではほとんど見なくなりましたよね、忠臣蔵。時代劇自体が減ってきているというのもありますが、作品のメッセージとしての忠義だとか仇討ちだとかが流石に古くなってきたようです。
ですが、演劇好きとして名作の粗筋を知っておくのは良いことだと思います。「仮名手本忠臣蔵」やシェイクスピアの「ロミオとジュリエット」、ミュージカルの「オペラ座の怪人」など、長きにわたって人々を楽しませてきた演劇作品の基礎を知っておくことは教養としても大事なのではないかな、とか判ったようなことを書いて今回のUFBを締めたいと思います。

本文とは関係ありませんが、先日信濃町辺りで見つけた慶應大学の「豫防醫學教室」は昭和四年築で現役の教室です。

粟根まこと
あわねまこと│64年生まれ、大阪府出身。85年から劇団☆新感線へ参加し、以降ほとんどの公演に出演。劇団外でも、ミュージカル、コメディ、時代劇など、多様な作品への客演歴を誇る。えんぶコラム「粟根まことの人物ウォッチング」でもお馴染み。
【出演予定】
劇団☆新感線「爆烈忠臣蔵」
【松本公演】
2025年9月19日(金)〜23日(火祝) まつもと市民芸術館
【大阪公演】
2025年10月9日(木)〜23日(木) フェスティバルホール
【東京公演】
2025年11月9(日)〜12月26日(金) 新橋演舞場