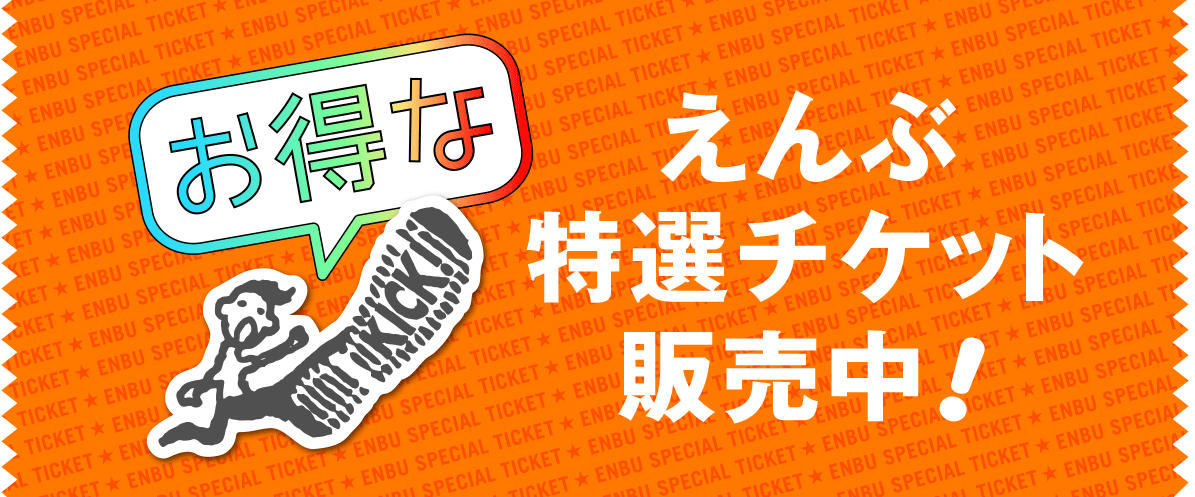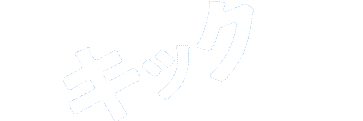「りゅうけん」
私の父の呼び名である。もちろん本名ではない。
私の中学時代の男子同級生たちがこっそり名付けた呼び名である。
泣く子も黙る、あの北斗のケンシロウの父親の名前で、拳術名の一種でもあるそうだ。
我が家では、命名から数十年経った今も、父の話で盛り上がる時はこの呼び名を拝借している。
かなり明け透けに乱用しているにも関わらず、どうやら本人は気づいていないようだ。
学生時代、娘に近づく男子には容赦しない。
いくら友達だと主張しても、ぎょろっとした丸い奥目で上から下まで舐めまわし、夜9時以降の電話は怒鳴り散らす。
成人した娘の門限は夜10時。
私が反抗すると「お前はヒメ(飼い犬)を放し飼いにできるか?」と来る。
いや、私は犬じゃない。
寒い真冬の駅のホーム、冷たい風が吹いて母が小さく震えると、新聞紙を大きく広げて風から母を守る。
満員電車がガタンと揺れると、人目をはばからず大きな声で「俺のベルトを持て!」と言う。
母が「恥ずかしいから止めて」と言っても関係アチャコ。
我が妻を守るのに周囲になんの遠慮があろうか。
荷物は必ず自分が持ち、歩くのはいつも車道側。
男たるもの強くあれ。
常に信念を持ち、規律を守り、決して弱さを見せない。
そう、我が父りゅうけんは、家族を守る正義の味方なのである。
りゅうけんは、終戦の二年前、日本で生まれた。双子だった。
産まれてすぐ双子の片割れは死んでしまい、下肢に軽い麻痺のあったりゅうけんの足は少し曲がっていた。
りゅうけんの両親、つまり私の祖父母は、戦前に韓国から日本に渡った。在日一世である。
悪化の一途をたどる戦下、寝る間も惜しんで働く日々。生まれたばかりの赤ん坊の面倒を見る余裕などなく、
一歳になったばかりのりゅうけんは、疎開を兼ねて、韓国済州島の曽祖母の元に預けられた。
曽祖母は、可愛い孫息子の少し曲がった小さな足を一日中さすってやった。
自分の両手をこすって温め、やさしく語りかけながら、毎日毎日さすり続けた。
そのおかげか、りゅうけんの曲がった足は見た目にほとんどわからなくなり、幼少時代には、麻痺の症状はすっかりなくなっていたそうだ。
りゅうけんは、済州島での記憶をほとんど話さない。覚えていないと言う。
曽祖母がいつも優しくニコニコしていたこと、
寡黙で怖かった曽祖父に叱られ、その仕返しに、近所の渋柿を獲ってきて渡したら、更にこっぴどくやられたこと。
そのぐらいである。
りゅうけんが幼少期を過ごした1944年~1954年の済州島は戦乱の真っ只中だった。
1945年の第二次世界大戦終戦後も、韓国の軍事政権下、“アカの島”と呼ばれ、3万人もの民間人が、国家権力によって無作為に虐殺された。
いわゆる4.3事件である。この民族大虐殺は、2000年までその事実を隠蔽された。
またその後の朝鮮戦争の勃発により、25万人もの島民の命が奪われたのである。
伝え聞いた話や資料によると、村では毎日叫び声が絶えず、村人は隠れる場所を探して洞窟に身を潜め、いつでも逃げられるよう常に小さな風呂敷包みを用意していたと言う。
そんな強烈な状況を、果たして父は本当に何も覚えていないのか、記憶から抹消してしまったのか、口を閉ざしているだけなのかは定かではない。
日本での商売に忙しく過ごしていた私の祖父は数年に一度しか済州島を訪れることができなかった。
小さなりゅうけんは、祖父に対して、「このメガネの人が僕のお父さんなのかな?」と、訝しげに思っていたらしい。
10歳になったある日、りゅうけんは、どこへ行くかも知らされず、同じ年頃の村の少年二人と船に乗せられた。
見つからないよう決して声を出すなとだけ言われ、暗い船底に身を潜めた。
捕まったら殺されるかもしれないと子供心に察知した。
抜き打ちのように見回りがやってくる。尖った長い針金のような棒で、隠れている隙間をつつかれるたびに、少年三人は身を寄せ合って縮こまった。
船底で、大好きなおじいちゃんとおばあちゃんから引き離された悲しみをこらえ、手に握らされたたった一つのリンゴを音を立てずに食べた。
大人たちに騙された悔しさと恐怖を静かに噛み砕いた。
その味は、たまらなく不味かったと言う。
いつも毅然としている父が唯一私たちに見せる弱点は、閉暗所恐怖症なのだが、私はこの話を聞いて、初めて合点がいった。
そしてたどり着いた青森の港に、たまに済州島を訪ねてきた、あのメガネのおじさんがいた。
「ああ、やっぱりこの人が僕のお父さんだったのか」。
りゅうけんはその時初めて確信したそうだ。
大阪での新生活が始まったりゅうけん少年の暮らしは一変した。
済州島での田舎暮らしとは違い、周囲はいつも忙しい。
住居兼靴工場になっていた家は、いつも大勢の大人たちがひしめき合っている。
ガチャンガチャンと裁断機の音が一日中鳴り響く。
靴の踵に釘を打つ音、靴裏に塗るゴムのにおい、ハネと呼ばれるヘップのバンドを縫うミシンの音、
おじさんたちの怒鳴り声、おばさんたちの笑い声。
父親らしきメガネのおじさん以外は、誰が誰だかわからない。
もちろん子供も大切な人手の一つだ。
りゅうけんもごった返す大人たちの隙間にちょこんと座り、
ミシンで縫われたヘップのハネを束にして紐で結び、幾つも幾つも積み上げて行く。
小学校に入学はしたものの、日本語はちんぷんかんぷん。
当然授業についていけず、言葉もわからないので友達もできない。
学校では喧嘩ばかりして、家では大人たちの邪魔にならないように内職を手伝う。
故郷の曽祖母の元に帰りたい、そんなやり場のない思いを胸に潜めて過ごしていたりゅうけん。
一年程過ぎた頃、勇気を出して、よく一緒に食事をするおばさんに尋ねた。
「僕のお母さんはどこですか?」
「アイゴ!今、この目の前にいるのがおまえのおかちゃんやないの!」
「そうか、この人がお母さんだったのか。」
りゅうけん少年は、それからようやくご飯をおかわりできるようになったそうだ。
しかし、幼少期を離れて過ごしたせいか、長男と言う重圧のせいか、
りゅうけんは、年の離れた妹や弟のように両親に甘えることはできなかった。
この少年は、泣いても喚いてもどうにもならないことがあるということを、皮膚感覚としてわかっており、
我慢することが身についてしまったのだ。
涙はただの水。過去を偲んで感傷的になったところで何も変わらない。
今目の前にあるものを黙々とこなし、先に向かって進むのみだ。
“ゆく河の流れは絶えずして、しかももとのみずにあらず”
父の口癖である。
強引で、周囲から見ればツッコミどころ満載の、揺るぎない父の正義は、この頃から確立されていったのかもしれない。
時は流れ、1960年代後半、この頃、地上の楽園と言われた北朝鮮への帰還者が後を絶たなかった。
終戦後、南北に分かれた朝鮮半島。同じ国にも関わらず、どちらかの国籍を選ばなければならなくなった在日朝鮮人たち。
約10万の在日たちが、この帰還事業で船に乗って北に向かった。
さて、りゅうけん18歳。
血気盛んでアイデンティティに悩む青春真っ只中。
意気揚々と入学した大学の青年同志たちと意気投合し、「われら今立ち上がれ!」と先頭に立って活動を始めた。
元来のやんちゃっぷりと統率力でみるみる人が集まり、昼夜、共産主義について信念を語り合った。
朝鮮半島の祖国統一に向けて、人権確立に向けて全てを注いだ。
祖国のために運動家になりたいと、家族の大反対を押し切って、北朝鮮に渡る船が出航する新潟の港まで出向いた。
しかし、いざ港に立ち、海を眺めていると、以前から少しずつ心の隅に浮かび上がっていたシラミのようなむず痒さが全身を覆う。
果たしてこれが正しいのだろうか、何かが腑に落ちない……。
自らの信ずるものへの疑念を取り払う事ができなくなった父は、その日を境にスパッと全てを捨てた。
活動も大学もやめた。
そして家業のヘップ工場を継いだ。
りゅうけんにグレーは存在しない。常に、白か黒なのである。
私はりゅうけんの涙を一度も見たことがない。
飼っていた犬や小鳥が死んだ時も、誰よりも世話をしていたにも関わらず、私たちに悲しむ時間も与えないまま、とっとと火葬してしまう。
祖父母が亡くなった時ですら涙一つ見せず、テキパキとお葬式の手配にかかる。
もちろん私の結婚式も、嫁ぐ娘に花向けの涙も見せない。
常に全力で前を向いて生きている父にとっては、過去の思い出は切り捨てるものなのか?と、非情に感じたことも少なくない。
“感傷”という文字はりゅうけんの辞書には存在しないのだ。
2013年、70歳のりゅうけんが心臓の大手術をすることになった。
家族中が動揺を隠し、“へっちゃら”を装った。
もちろんりゅうけんも、涙どころか気弱な素振りなどは一切見せない。
手術当日、仕事で韓国にいた親不孝の私は、手術直前のりゅうけんと国際電話で話した。
いつもの強気と違って、なんだかボソボソと力ない声で話すりゅうけんに、嫌な緊張が走り、思わずこみ上げるものを必死で押さえ、
へっちゃらを装って、全力で耳を傾けた。
りゅうけんはとにかく喋り続けている。
「ええか。手術で心臓を一回取り出すってことは生まれ変わるようなもんや。
だからな、アボジは明日から改名する。ほんまはあんまり名前気に入ってなかったんや。
今度はな、“龍”に“雲”と書いて“龍雲(りゅううん)”にするんや。
天高く登る龍や。どや、かっこいいやろ?」
「……ん?あれ?……えっと、お父様?
そもそもあなた様のお名前は“りゅうけん”ではありませんが……?
ってか、ってことは、“りゅうけん“って呼ばれてること知ってたんか~い!」
これぞ完璧なコント。緊張と緩和。
私は思わず吹き出し、ツッコミたい気持ちをグッと押さえて、
「そうやね、じゃこれからは“りゅううん”にしよう。」と、優しい娘を演じきる。
天高く上る龍の如く、
見事な生還を果たしたりゅうけん、もとい、龍雲は、
退院早々に漢字検定を受験し、俳句を始め、いきなり全国特選2位に輝く偉業を達成。
その名に恥じず、高く高く、新たな世界に向けて昇り続けている。
生誕76年の誕生日。
弟夫婦や孫たちと共にのんびり暮らすりゅうけん。
親不孝な娘が、手抜きして電話でおめでとうと伝えると、
「おお。今、孫たちとメロンに立てたろうそくを消したところや。アボジもおじいちゃんと同じ年になったで。」
「おじいちゃん?」
「そうや。アボジのおじいちゃん。お前のひいおじいちゃん。ひいおじいちゃんが死んだ年や。」
「え、なんで今、ひいおじいちゃんの話?」
「子供の頃な、済州島のおじいちゃんとな、明け方、まだ月が出てるうちに舟に乗って海に出るんや。おじいちゃん、漁師やったからな。」
「へえ。そんな話初めて聞いた。」
「そうか?それが楽しみでな。その日は朝起こされる前に目が覚めるんや。」
「ひいおじいちゃんのこと好きやったんやね。」
「めちゃくちゃ怖かったけどな。せやなぁ、好きやったなぁ。」
「全然知らんかった。」
「せやったか?あの舟のことはしょっちゅう夢に出てくるで。ヘミングウェイの“老人と海”や。格好ええやろ?アボジもおじいちゃんと同じ年や。」
笑っている父の声が詰まった。
私は耳を疑った。気づかないフリをした。涙が止まらなくなった。
小さな少年は、舟の上で、怖くて大好きなおじいちゃんとどんな話をしていたのだろう。
いや、きっと76歳になるまで、何度も何度も夢の中でおじいちゃんと話していたのだろう。
男たるもの強くあれ。涙を見せるな。家族を守れ。
私たち家族を守るため、弱音を吐かず、嫌われても勘違いされてもへっちゃらを装うために、
きっと何度も舟のおじいちゃんに会いに行っていたのだろう。
私は、初めて父の心臓に触れた気がした。

****************
<みょんみょんの韓国語教室>
女優みょんふぁと一緒に遊びながら韓国語をマスター
진짜 좋아요!(チンチャ チョアヨ)めっちゃ素敵!

著者プロフィール

みょんふぁ
女優やナレーション・司会業を中心に、日韓の通訳翻訳や戯曲の紹介など公演のプロデュースも行う。
在外研修で韓国国立劇団に留学、韓国デビューし、小田島雄志翻訳戯曲賞受賞。
現在、日韓演劇交流センター副会長。
映画・舞台・ドラマなど多数出演。昨今は日韓合同制作作品にも多数出演。
日韓交流の拡大化のために母体となるSORIFAを設立し、代表を務める。
●Youtubeチャンネル みょんふぁ(SORIFA)チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCI2ITpnZzwAlruYJ6eVCNwA
●HP〜花笑み時間〜
https://myonpappa.amebaownd.com/
●ブログ〜遊びをせんとや生まれけむ〜
https://ameblo.jp/myonpappa