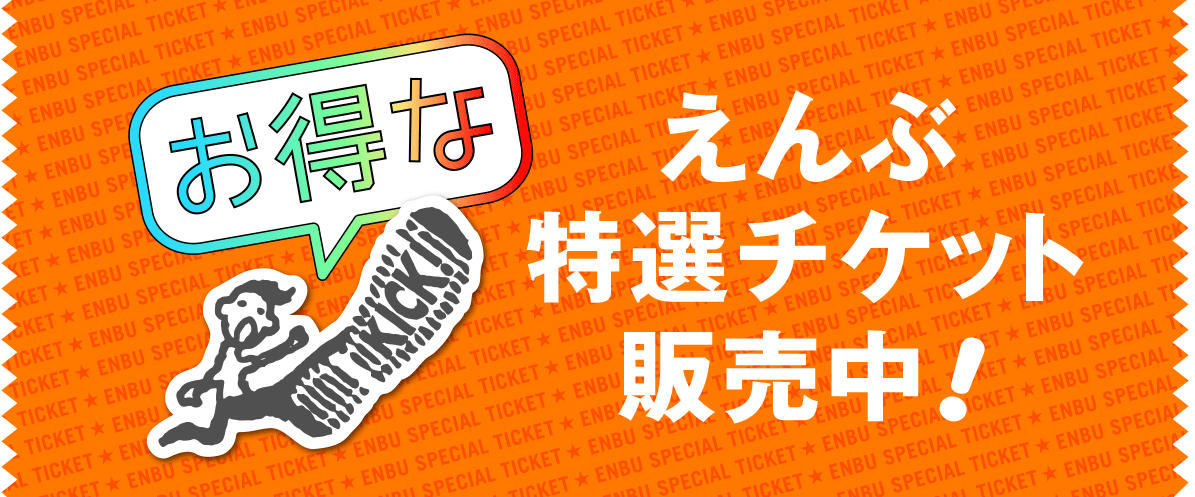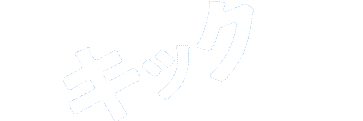ここからはじまる「未来へ」宝塚宙組『Le Grand Escalier─ル・グラン・エスカリエ』
宝塚歌劇宙組特別公演『Le Grand Escalier─ル・グラン・エスカリエ』が、東京宝塚劇場で上演中だ(25日まで)
『Le Grand Escalier─ル・グラン・エスカリエ』は、宝塚歌劇を象徴する代表的な舞台装置のひとつである、眩く輝く「大階段」をタイトルにした齋藤吉正作・演出による80分のレビュー。1927年に欧米視察から帰国した岸田辰彌によって上演された、日本初のレビュー作品『吾が巴里よ〈モン・パリ〉』以来、宝塚が連綿と繋ぎ続けてきたレビューの歴史を振り返るというコンセプトで、宝塚レビューの名曲と共に、その醍醐味が盛りだくさんに、しかも滑らかに紡がれていく。近年のレビュー作品としては80分の上演時間はかなりの長尺だが、飽きさせることなく、むしろあっという間に感じさせるほどバラエティー豊かにその魅力が詰め込まれた内容だった。ここには、ほぼ確信犯的に異端児であり続けてきた齋藤吉正が、実は立派なベテラン作家として成熟していることが顕著に表われていて、齋藤自身がおそらく、この仕事に臨むにあたり、そうした自己プロデュースよりも作品と宙組と、つまりは宝塚への献身を選んだことが見て取れた。
中でも素晴らしかったのは、耳に馴染んだ数々のレビュー、ショー作品の主題歌だけでなく『ダル・レークの恋』の「まことの愛」や『哀しみのコルドバ』の「コルドバの光と影」と言った、折に触れて再演が繰り返されてきた芝居ものの作品に書かれた楽曲を、レビューのなかに持ち込んでみせたことだ。それによって楽曲の持つドラマ性が、ミステリアスなパリの夜や、スペインのマタドールが向かう闘牛場といった、レビューシーンの一つひとつを色濃く描き出す力になっている。これはやはり前述したように80分のレビューに大きなメリハリをつけるものになったし、トップスターの芹香斗亜がコミカルな明るい役柄を得意とすることを計算に入れたであろう、ダウンタウンのニューヨーカーのシーンなどの陽性な場面との見事なコントラストを生む効果になった。
もうひとつの大きな特徴は、トップ娘役の春乃さくらを筆頭に、娘役を男役の相手役としてだけではなく、レビューを華やかに表出する一人のスターである、という場面配置を施したことだ。これは近年の宝塚を見慣れた方々には、ある種革新的に見えるかもしれないが、それこそ今年50周年を迎えた『ベルサイユのばら』初演で開演アナウンスを担ったのがマリー・アントワネット役の初風諄だったように、宝塚110年の歴史のなかには、娘役の大スターは数多くいた。だから宝塚レビューの歴史をひもとくこの作品で、娘役が芯になるシーンがいくつもあったことは、まさしく温故知新に他ならず、その大任を春乃がこれほどまでに弾けられる人だったのか、と感嘆するほどのパッショネイトを持って堂々と歌い踊ったことは特筆に値する。『エスカイヤ・ガールズ』の同名主題歌を、新進娘役の湖々さくら、愛未サラ、美星帆那の三人だけに丸々任せたのも、いまのレビューでは非常に新鮮で、こうした流れは是非これからも活用していって欲しい。それは、実は全員女性だから、というパラドックスで保たれていた、センターは必ず男役という宝塚のセオリーに、いまの時代に相応しい多様性を持ち込める風にもなると思う。
だからと言ってもちろん、男役たちの大活躍ぶりは少しも減じてはいない。中でも芹香と並び立ったに近いほどの場を得た桜木みなとの充実ぶりは頼もしい限りで、やはり宝塚歌劇史上に残る大スター鳳蘭の為に書かれたショー『セ・マニフィーク』の主題歌を、ここまで見事に現代に蘇らせたのは桜木が初めてではないかと感じたほどだった。と言うのもこの楽曲で手拍子が入ることを鳳は好まない。それほど彼女自身の卓越したリズム感、グルーヴの赴くままに、自由で縦横無尽な「鳳ワールド」に劇場を巻き込むのが、鳳の歌う「セ・マニフィーク」の真骨頂だからだ。けれども桜木のそれは、客席中から賑やかな手拍子を引き出し、それに乗って、また乗せられて、あくまでも明るいエネルギーとパッション全開で歌われる、全く新しい「セ・マニフィーク」だった。宝塚レビューの歴史を振り返る『Le Grand Escalier─ル・グラン・エスカリエ』で、この感触が得られたことは大きい。先に述べた「まことの愛」をはじめ、豊かな歌唱力を存分に発揮した瑠風輝。このレビューでのジャンプアップが顕著で、そのスター性の貴重さを改めて感じさせた風色日向。やはりこれからの活躍が多いに期待できる逸材だと思わせる亜音有星をはじめ、若手男役たちが揃って歌えることもレビューだけで魅せるこの作品に大きく貢献している。
更に作者である齋藤自身の大劇場デビュー作であり、今もあまりにも鮮烈な記憶を残している『BLUE・MOON・BLUE 』の再構築場面が盛り込まれたのは、ひとつのエポックメイキングだった。この作品は初演当時の真琴つばさ、檀れい、紫吹淳のトリオへのあてがきが見事過ぎたが故に、別のメンバーでの再演がちょっと想像できない、謂わば『セ・マニフィーク』と同じ立ち位置にある金字塔だった。それが芹香、春乃、鷹翔千空のトリオで再構築され、妖花=赤い花から、妖鳥となった春乃が共に踊り芹香の旅人をジャングルの魔境に取り込み、鷹翔の蛇が「BLUE ILLUSION 」を嵐之真のソロも挟みながら高い歌唱力で歌いあげる、謂わば令和の『BLUE・MOON・BLUE 』が立ち上がったのは、このレビュー全体の白眉。ふとした時に少年のような表情も見せる芹香が、蛇と妖鳥ダミーの水音志保、山吹ひばり、渚ゆり、結沙かのんという美女揃いの娘役たちに誘われてジャングルに迷い込んでくる時に、宝塚の名曲中の名曲『ザ・レビュー』の「夢人」を歌うという、まさかのコラボレーションに全く違和感がないのにも驚かされたし、一人取り残される旅人がこちらも歌い継がれるべき名曲「ENDLESS DREAM」を歌う終盤まで、まるで一篇のドラマを観る心持ちがした。これらピックアップした場面だけでなく、タイトルの「大階段」が輝くフィナーレのパレードまで、非常に質の高いレビュー作品になっていて、大作=ミュージカルの1本立てという認識が、宝塚歌劇団の根底にはあるように推察されるが、レビューは宝塚ファンに非常に好まれている作品形態だし、若手まで多くの人材が活躍できることも併せると、こうしたレビューだけという公演が、5組からなる年間ラインナップのなかにひと公演あってもいいかもしれない、そんな未来への可能性も感じさせる舞台だった。
そう未来だ。いまこうして宙組特別公演が行われていることには、東京宝塚劇場を埋めている2千人の観客一人ひとりに、2千通りの考え方、受けとめ方があると思う。実際に私自身、レビューの最終盤、第10章で『エクスカリバー』の主題歌「未来へ」が歌われた折には、宙組が宝塚5番目の新組として誕生した1998年のあの日、全てが未来への希望に満ちていたあの日を思い、胸迫るものがあった。同様に作品を観た人だけではなく、観なかったという人にも様々な想いがあるだろうし、悲しみや悔いや怒りや悼む気持ち、それを越えて尚生まれる情熱もあるだろう。そのどれひとつをとっても、間違っているものはない。どんなに異なる意見であっても、幾星霜の想いの全ては、元はと言えば宝塚歌劇団への、そして歌劇団生への愛から生まれている。誰もが愛からはじまったあらゆる感情に、傷ついてもいるし、こうあって欲しいという願いとそれぞれの判断がある。それでいい、全てが正しい。
ただ巻き戻せない時間のなかで、ここからはじまる「未来へ」の歩みを私は見つめていこうと思う。110年も続いてきた歴史のなかで、気づかないうちにいまの世の中とは乖離していったものがあるのは、ある意味無理もないことだ。それこそ演劇現場の演出家像と言えば、俳優に罵詈雑言を浴びせながら灰皿を投げつける……、という光景が当然のように語られていた時代は確かにあった。だが、いま日本を代表する、演出家の名前で人が集まると称される第一線の演出家たちのほとんどが、まず褒める、そして褒めた上でそこから新たなアイディアを共に考えていくという演出スタイルをとっている。それで作品の質が落ちたなどということは決してない。時代はかくも動いていて、意識さえ変えれば現場は変えられる。変えていって欲しいし、きっと変えてくれる。だからこそこの舞台が幕を開けたのだと信じたい。
そんな思いは、トップコンビの「大階段」のデュエットダンスに、やはりミュージカル作品『王家に捧ぐ歌』の主題歌「世界に求む─王家に捧ぐ歌─」が選択されたことと奇しくもシンクロしている。オペラ『アイーダ』を基に木村信司の書いたこの曲の歌詞には、例えいまは夢のように思えたとしても、戦いに終わりを告げて、人が皆等しく認めあい、お互いを赦せる、そんな世界を築いていこう、という尊い希望が込められているのだ。
愛から生まれた様々な幾千万の想いのなかから、そんな明日を見つめていきたい。宝塚の、宙組の、全く新しい未来への第一歩がここからはじまることを祈り、願っている。
【公演情報】
宝塚歌劇宙組公演
『Le Grand Escalier─ル・グラン・エスカリエ』
作・演出◇齋藤吉正
出演◇芹香斗亜 春乃さくら ほか宙組
●7/20~8/25◎東京宝塚劇場
【取材・文/橘涼香 撮影/岩村美佳】