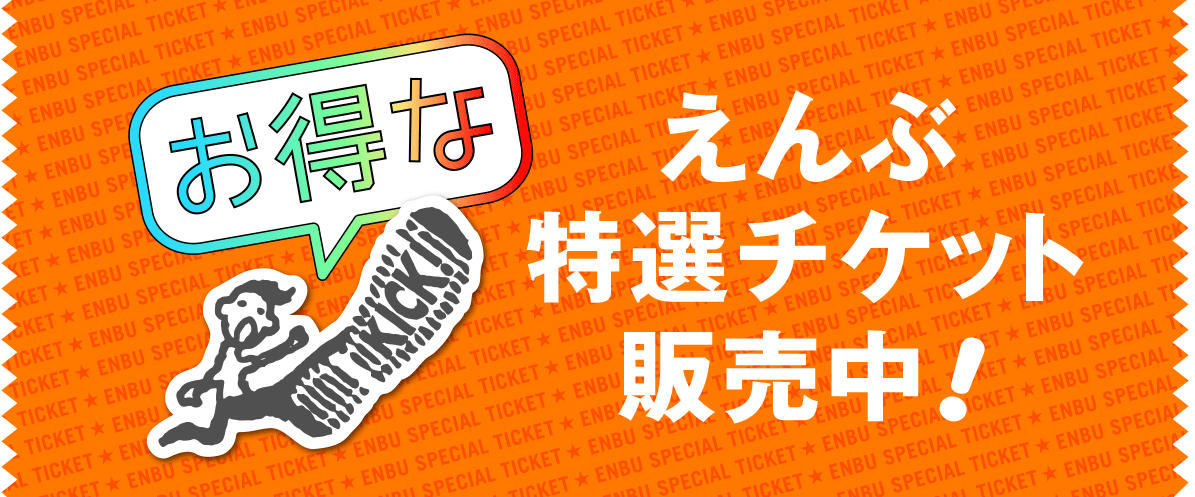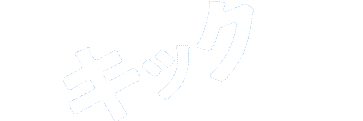歌舞伎座7月公演、松竹創業百三十周年「七月大歌舞伎(しちがつおおかぶき)」が、7月5日に初日の幕を開けた。彩り豊かな演目で猛暑を吹き飛ばす舞台を堪能できる。
昼の部では、江戸から明治にかけて活躍し現在に繋がる近代歌舞伎の礎を築いた九世市川團十郎が、史実・時代考証に則った活歴物や新たな松羽目物を中心に制定した「新歌舞伎十八番」から『大森彦七』、『船弁慶』、『高時』、『紅葉狩』の4演目を一挙上演。これまで例のない4演目一挙上演で、歌舞伎座に新たな歴史を刻む。
【昼の部】

26年ぶりの上演となる『大森彦七(おおもりひこしち)』は、明治時代に九世團十郎が提唱、実践した時代考証による扮装や演出を取り入れた「活歴物」と呼ばれるジャンルの作品。
舞台は南北朝時代、南朝方の楠正成を討ち取った武将・大森彦七(市川右團次)と正成の息女・千早姫(大谷廣松)の出会いから描かれる。鬼女の面をつけて父の仇である彦七に斬りかかる千早姫。それを組み伏せた彦七が、正成の潔い最期の様子を語る「物語」の件では、彦七が紡ぐ言葉に観客が引き込まれる。

父の形見の菊水の宝剣を渡し、姫を逃がしてやる彦七は、やがて姫の正体を察する道後左衛門(市川九團次)に、狂気を装って正成の怨霊に宝剣が奪われたと紛らわす。彦七が乗った馬も踊る珍しい趣向で、豪快に花道を引っ込むと大きな拍手が送られた。
続いては『船弁慶(ふなべんけい)』。

兄の頼朝に謀反の嫌疑をかけられ、都を追われた源義経(中村虎之介)は、大物浦まで同道してきた義経の愛妾・静御前(市川團十郎)に都へ帰るようにと告げ、静は悲しみを堪えて舞を舞う。都の名所の四季の移ろいを描く「都名所」の舞は、前半の見どころ。しなやかな所作一つ一つに義経への想いが溢れ、観客の視線を引き込んでいく。
やがて、舟長三保太夫(中村梅玉)が舟人(坂東巳之助・中村福之助)と共に船出を祝う住吉踊りを舞うと、軽快な踊りに舞台が華やぐ。

舟長の音頭で船出する一行だが、突如雲行きが怪しくなり、緊張感溢れる中、花道から現れるのは、平知盛の霊(團十郎/二役目)。平家を滅ばされた恨みを晴らそうと凄まじい勢いで義経一行に迫る。弁慶に祈り伏せられた知盛の霊の花道の引っ込みは、渦潮とともに水底へ姿を消す壮絶な様子を描く。大きな長刀を華麗に振りかざす姿に場内の熱気も高まり、万雷の拍手が響き渡った。
鎌倉幕府末期の執権・北条高時を描いた『高時(たかとき)』。

北条高時(坂東巳之助)は、犬を偏愛し、田楽にうつつを抜かす驕慢ぶり。愛犬を斬った安達三郎(中村福之助)に死罪を命じ、横暴な姿を見せる。愛妾衣笠(市川笑三郎)の酌で飲んでいると、そこへ突如雷鳴が響き渡り、天狗たちが現れて…。

/
天狗にたぶらかされて田楽舞に興じる「天狗舞」では、巳之助がとんぼを返るなど驚異的な身体性を見せ、客席を沸かす。幕切れ、高時が虚空を睨んで「北条九代連綿なる」という名台詞と、片方の肩を落とした美しい姿で決まると、幻想的な世界観が観客を魅了した。
そして最後は、『紅葉狩(もみじがり)』。

幕が開くと、紅葉が美しい戸隠山。平維茂(松本幸四郎)は、従者を伴い紅葉狩に訪れると、ひと足先に宴を催している美しい更科姫(市川團十郎)の一行に誘われて、酒を酌み交わす。侍女・野菊(市川ぼたん)はじめ、更科姫が艶やかな舞を披露すると、維茂とともに観客もうっとりと心奪われる。そこへ現れた山神(市川新之助)に、更科姫の正体を告げられ…。

團十郎、ぼたん、新之助の成田屋親子が顔を揃える舞台に客席は沸き上がり、後半の維茂と鬼女のダイナミックな立廻りに大きな拍手が送られた。團十郎勤める迫力満点の鬼女と、幸四郎勤める凛々しい維茂との立廻りに目が釘付けとなり、華やかに幕を閉じた。

【公演情報】
令和7年7月歌舞伎座松竹創業百三十周年「七月大歌舞伎」
日程:7月5日(土)~26日(土)[休演]11日(金)、18日(金)
会場:歌舞伎座
https://www.kabuki-bito.jp/theaters/kabukiza/play/935