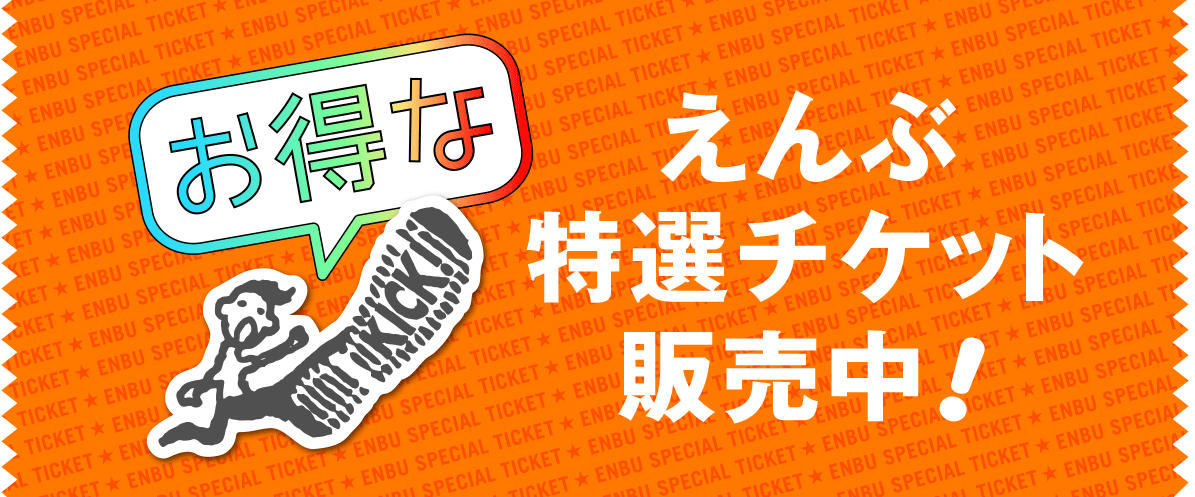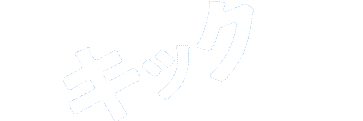一色洋平×小沢道成の二人芝居『漸近線、重なれ』が、4月1日~4月7日に、新宿シアタートップスにて上演される。
脚本は演劇ユニット「Mo’xtra」主宰の須貝英、音楽はオレノグラフィティが担う。彼らがタッグを組むのは2016年上演『巣穴で祈る遭難者』以来8年ぶり、3作目となる。開幕まで1ヶ月を切った3月上旬、一色と小沢が作品創作に打ち込む稽古場を訪問した。
漸近線(ぜんきんせん)とは数学用語で、グラフ上で曲線と限りなく距離が近付いているのに交わらない直線のこと。タイトルを発案したのは脚本の須貝だが、もしかしたら一色と小沢の思いが反映されているのかもしれない、と二人は話す。文学的でアカデミックなテーマ、重厚なタイトルのほうが演出で遊び甲斐があるのでは、という意向は1作目の『谺は決して吼えない』から継続しているそうだ。それに加えて今回、企画段階で「二つの一人芝居が並走しているような、交わらない二人芝居をやりたい」と提案した小沢と、それを受けて「いや、やっぱりせっかくなら交わりたい」と言った一色。そんな思いを、交わりそうで交わらない「漸近線」に昇華させたのではないか。そう語る彼らの表情から、創作を心から楽しんでいること、そして脚本に対する愛情がひしひしと伝わってきた。

本作は、地元を離れ地方都市にやってきた郵便局員の水野要(みずの かなめ)を一色が、水野以外の全ての登場人物(なんと総勢13人!)を小沢が演じる。水野が暮らすアパートを舞台に個性豊かな住人たちとのやり取りを描き、普通の住居とは一味違う、一色と小沢が考案した美術セット(詳細は開幕までお楽しみに)で、ほっこり、ときにちょっぴり切ない会話劇が繰り広げられる。そして、物語の軸となっているのが旧友の山部泰親(やまべ やすちか)との手紙の往来である。

この日の稽古は、小沢のパートを稽古場代役の粂川鴻太が担い、小沢が演出をつけていくスタイルで進行した。水野が山部から届いた手紙を読む場面で、小沢が一色に細かく感情の動きを問いながら稽古を進めていたのが印象的だ。「手紙の中の、特にどの言葉をつらいと思った?どこがフックになるかな?どこで前に進めそう?」
それに対して一色は、手紙に書かれている言葉をとても大事そうに一言ずつピックアップし、山部の優しさや救済を逆につらく感じてしまうこと、彼が幸せのさらに先へ向かっていることへの焦り、前回自分が送った手紙のせいで相手の気持ちを変化させてしまったことに対する罪悪感を吐露する。たった一言に様々な解釈が考えられ、感情をどう演技で表現するのが正解なのか非常に難しい場面だが、小沢は「言葉が感情を連れてってくれるから、構えなくていい。」と話す。

稽古中、彼らの間で「言葉でフタをする。」というワードが何度も出てきた。ふつふつと沸騰している感情を、垂れ流すのではなく言葉で一度封じ込める。それでも隙間からどうしても溢れ出てしまうものこそが表現になるのだと。あえてフラットに伝えることで、より観客の心に言葉がダイレクトに届くことがきちんと計算されている。
また、手紙に書かれたネガティブな言葉をどう捉えるかについて小沢は「声に出すということは、打ち勝とうとしている。なんとかしようとしている。“負けんな俺”ってずっと言ってる。この手紙を読む水野には、苦しいからこそ、声に出そうとする強さがある。」と説く。些細な近況報告も相手が大切な人であればあるほど心が抉られる。文字で読むと、対面での会話とは違い表情や声色が伝わらない分、冷たく感じることもある。相手に悪気がなくても自分が傷付いてしまったら、きっとそれが自分の本当の気持ちで、素直に受け入れるしかないのだ。手紙を読み終えた水野は次のシーンで、ある一つのアクションを起こす。彼が一歩前進するための重要な場面である。

さらに小沢は「言葉と感情のバランスが大切だ。」とも話す。
実生活において、事象のクライマックスと感情のピークに時差が発生すると感じたことのある人は、きっと少なくないはずだ。アクシデントが起きたときや、良くも悪くも胸を突く言葉を投げかけられたとき、感情が追い付かないまま、とにかくその場を取り繕うのに精一杯で、一息ついてやっと喜びや悲しみや怒りがどばどばと溢れ出してくる。
おそらくそれは観劇にも通じることだ。舞台上で発せられた言葉を観客が噛みしめ飲み込み、心に浸透させるための余韻作りが、小沢は抜群に上手い。登場人物の動きやセリフの間合いが緻密に作り上げられた演出は、見る者の感情の揺れとピタッとタイミングが合致する。

彼らがタッグを組むにあたり、2作目までは空気感を大事にし、面白そうな道を感覚で選んで後から意味をつけていたこともあったそうだが、今作はいくら面白くても筋が通っていないアイディアは採用しないという。そんな小沢の取捨選択を、一色は「英断だ。」と称える。美術、音楽、演技、転換。作品を司る全てが意味を持つ。そうやって一つ一つ、嘘なく妥協せず積み重ねていく誠実さが、作品全体のクオリティー向上に繋がっているのだろう。総合芸術である演劇に対しての深い理解と愛を感じた。
稽古中盤、ある小道具が新たに稽古場に到着した。水野が暮らす部屋に置かれる大切なアイテムである。到着までは演出部スタッフの松嶋柚子が手作りした仮小道具で稽古をしていたのだが、それがなんとも丁寧で可愛らしい作りなのだ。仮小道具は大きさと形さえ本物と合致してれば稽古は成り立つ。けれど、より役者が演技をしやすいようにデザインにひと工夫加えるスタッフの配慮。そして、それにしっかり気付いて感謝を伝える小沢と一色の優しさに、なんて素敵な現場なのだろうと胸を打たれた。まさに、小道具一つにもしっかりと意味があることを目の当たりにした瞬間でもあった。

普段EPOCH MANで自ら脚本を書いている小沢は、須貝が書いた物語を扱うことに対して「他者の気持ちを知る難しさに直面している。なぜこの言葉を書いたのか、全部はわかりきれないけれど、自分の身体を通して他者を演じることでわかろうとするのが役者の仕事だと思う。」と話す。
一色は「言葉だけでなく句読点にも意味があると感じているし、今回は1作目、2作目に増して言葉を大事にできている自覚がある。千穐楽まで脚本ファーストの気持ちを持ち続けたい。」と脚本へのリスペクトを覗かせた。
そして須貝の脚本に対して、小沢が「僕がいつも作ろうとしているものと近い」、一色は「台詞が口に馴染む」と言った通り、彼らの相性の良さ、全員が同じ方向を向いて作品創作を進めていることで生まれるまとまりを感じた。

小沢は本作を「希望の話だ。私も頑張ろう、生きようと思える作品。」と語る。その希望は決して、絶望の底に沈んでいる人をずるずると明るい場所に引っ張り上げるようなものではなく、しんどさを両腕いっぱいに抱えた人を、その荷物ごと包み込むあたたかさを持っている。景色が目まぐるしく移り変わる春という季節に足がすくんでしまう人にこそ、劇場に向けて一歩、その足を踏み出すことをお勧めしたい。
(取材・文:村田紫音 撮影:一色健人)

【公演情報】
一色洋平×小沢道成『漸近線、重なれ』 presented by EPOCH MAN
出演:一色洋平 小沢道成
演出・美術:小沢道成 一色洋平
脚本:須貝英
音楽:オレノグラフィティ
●2024/4/1~7◎新宿シアタートップス
〈料金〉前売・当日共/5,500円 U22チケット2,500円[要年齢確認証](全席指定・税込・未就学児童入場不可)
※前方エリア・後方エリアをお選びいただけます
〈お問い合わせ〉epochman.info@gmail.com
〈公演サイト〉https://epochman.com/zenkinsen.html
〈公式サイト〉https://epochman.com/
〈公式X〉一色洋平 @yohei_isshiki 小沢道成 @MichinariOzawa
〈YouTube〉https://www.youtube.com/c/EPOCHMAN